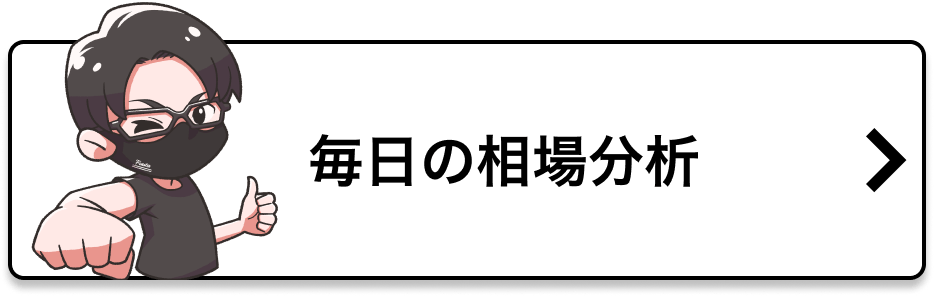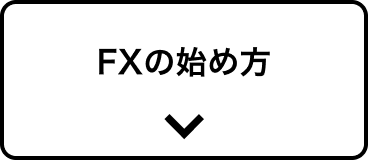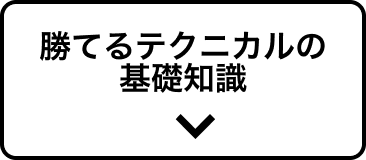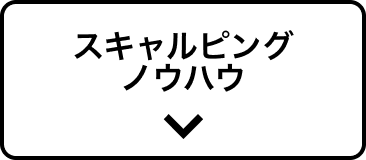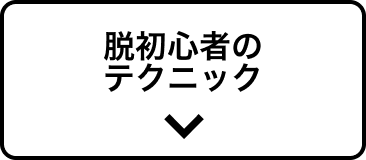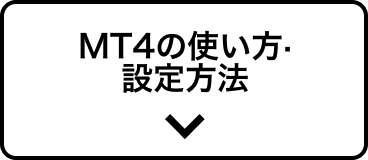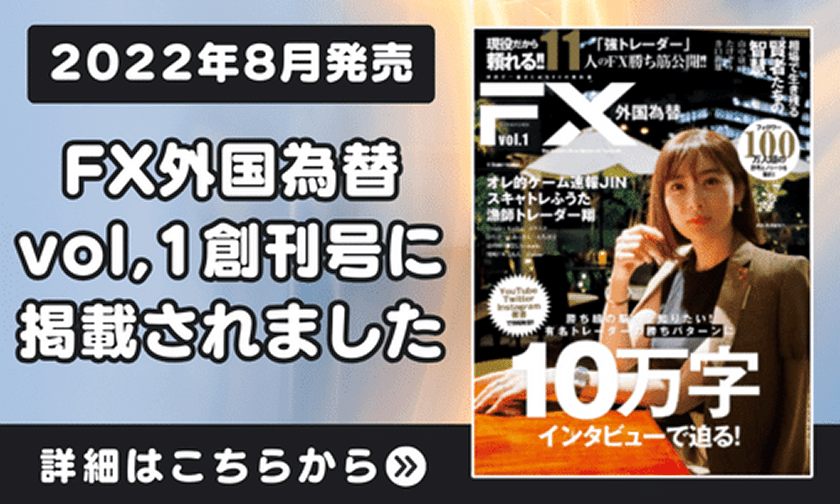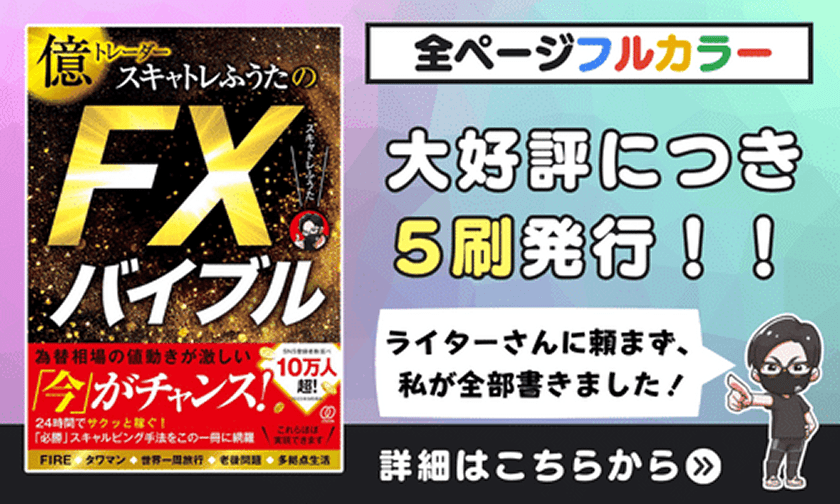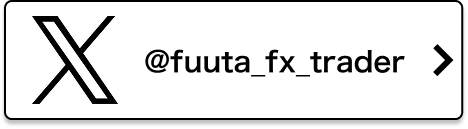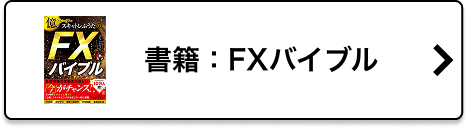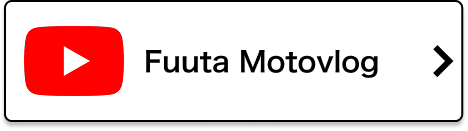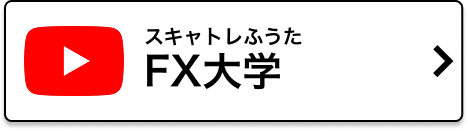【FX初心者が逆行・だまし・チキン利食いを防ぐ!】ボリンジャーバンドと移動平均線で損しない戦略
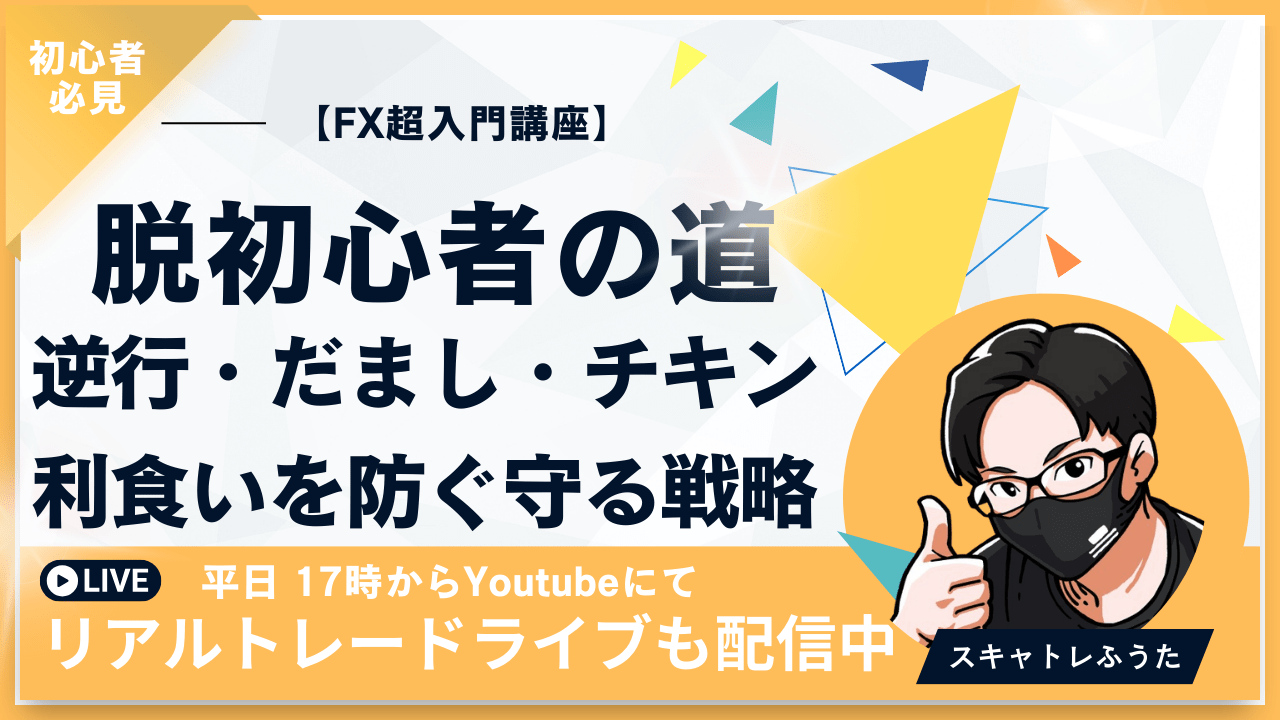
トレードしていて「自分がエントリーした瞬間だけ逆に動く」「誰かが見ているんじゃないか」と感じたことは、誰にでもあるのではないでしょうか。私も初心者時代、まさに同じ気持ちでした。ですが、これは「見られているから」ではなく、「トレードの理解が浅いから」起こる現象です。
たとえば、ボリンジャーバンドの±3σで逆張りエントリーしても反転しない。それは実は上位足でトレンドが発生していて、押し戻しが起きにくいタイミングだったということもよくありました。
こうした「なぜ失敗したのか」を振り返り、マルチタイムフレームでの環境認識を持つことが、トレードの勝率向上につながります。

ここからは、「逆行」「反転しない」「チキン利食い」「ゴールデンクロスで勝てない」など、よくある悩みに対して、私が実践している具体的な対処法をご紹介します。
これからFXを始める初心者に観てほしい動画です。
ボリンジャーバンドで反転しないのはなぜか
短期足のボリバンだけで反転を狙うのは危険
ボリンジャーバンドの±2σや±3σを見て、「そろそろ反転するだろう」とエントリーするのは初心者によくある行動です。しかし、短期足のボリバンだけを根拠にしてしまうと、実際には反転せずに逆行するケースが非常に多くなります。なぜなら、短期足はノイズが多く、相場全体のトレンドや背景を反映しきれないからです。
特に1分足や5分足では、その時点の一時的な動きが目立ちやすく、本来の流れとズレたタイミングでエントリーしてしまうことも少なくありません。「バンドにタッチしたら反発する」という考えだけに頼るのではなく、その価格が“どのような流れの中にあるのか”を考える必要があります。
私自身も初心者の頃は、5分足の−2σでロングすればすぐ戻ると信じていましたが、実際はそのまま下落が続いて損切りに至ることが多くありました。

反転を狙うなら、まずは上位足と照らし合わせてトレンドの方向性を確認したうえで、短期足のバンドタッチが“押し目”や“戻り”に当たるかを見極めましょう。
トレンド発生時はエクスパンションに要注意
ボリンジャーバンドが反転せずそのまま伸びてしまう場面では、多くの場合「エクスパンション」が起こっています。これは、バンドが拡大しながらトレンド方向に勢いが増していく局面です。バンドが開いている最中は価格がその方向に張り付くように進むため、逆張りは非常に危険です。
エクスパンションが発生すると、価格は一方向に強く動き続ける性質があるため、±3σだからといって反発を期待して入ると、そのままトレンドに飲み込まれて損失になります。特に、上位足も同じ方向に勢いづいている場合は、逆張りではなく順張りの視点が重要です。
私も経験がありますが、バンドが開いているのに「ここまで来たから反転だろう」と逆張りして、何度もそのまま持っていかれたことがありました。今では、バンドの傾きや広がりを確認して、「これはエクスパンション中だな」と判断したら、逆張りは避けています。

反転を狙うよりも、トレンドの流れに素直に乗ることで、結果的に利益を伸ばしやすくなります。ボリバンを見るときは、バンドの形状と動きにも注目しましょう。
上位足とのズレをマルチタイム分析で補正する
ボリンジャーバンドを使って反転を狙うには、「今の動きが上位足の流れとどう関係しているか」を知ることが欠かせません。短期足での反転ポイントに見えても、上位足で見ると単なる調整の一部だった、ということはよくあります。
マルチタイムフレーム分析では、自分が見るべき複数の時間軸(たとえば1分足・5分足・15分足・1時間足)を意識して、全体の流れを捉える必要があります。上位足が強い上昇トレンドを形成しているなら、短期足のボリバン−2σに到達しても、それは逆張りのチャンスではなく“押し目”の可能性として判断すべきです。
私も以前は短期足だけに頼っていたため、反発を狙ってエントリーしては、上位足のトレンドに巻き込まれて損をする…というパターンを何度も経験しました。ですが、上位足の動きを確認する習慣をつけてからは、逆行に悩まされることが減ってきました。
エントリー前には、必ず上位足のボリンジャーバンドの傾きや位置関係を確認し、自分が見ている足が全体の流れと矛盾していないかをチェックしましょう。

これが、反転の精度を高める大きなポイントになります。
高値掴み・安値掴みが多くなる本当の理由
飛び乗りエントリーが失敗の原因になる
相場が勢いよく動いているとき、「今しかない!」という気持ちで飛び乗ってしまうことはよくあります。しかし、この“飛び乗りエントリー”は高値掴みや安値掴みの最大の原因になります。勢いに乗ろうとしても、その直後に反転するケースは非常に多く、特にレンジ相場やだましが出やすい場面ではリスクが高まるでしょう。
値動きに反応してしまい冷静な判断ができないと、エントリーの根拠が薄くなり、損切りされる確率が高くなります。相場は常に上下に揺れながら動いており、急激な上昇や下落のあとは調整が入ることが多いため、焦って飛び乗るほど不利な価格でポジションを取ってしまうのです。
私自身、以前は「今動いたから入らなきゃ」と思って飛び乗り、結果として反転されるパターンに何度も苦しみました。後から見返すと「あと数分待てばよかった」という場面ばかりです。

エントリーは、感情ではなく根拠で行うもの。飛び乗りたくなる場面こそ、いったん落ち着いて相場の背景や上位足の状況を確認するようにしましょう。
オシレーターのみに頼ると騙されやすい
RSIやストキャスティクスなどのオシレーター指標は、「買われすぎ」「売られすぎ」の状態を示す便利なツールです。しかし、これらの指標に頼りすぎると、反転を狙ったつもりがそのままトレンドに巻き込まれて損切り…という失敗を招きやすくなります。
特に強いトレンド相場では、オシレーターが“買われすぎ”のまま上昇を続けたり、“売られすぎ”のまま下落が続いたりするため、単純に数値だけを見てエントリーしてしまうと、逆行されるリスクが高まります。
私も以前、RSIが70を超えたらショート、30を下回ったらロングという判断をしていましたが、強いトレンドではまったく機能せず、「売られすぎ=買い」ではないと痛感しました。オシレーターはあくまで“補助的な参考指標”であるべきです。

オシレーターのシグナルを使う際は、必ずトレンドの有無やチャートパターンと組み合わせ、反転の兆しが出ているかを複合的に判断しましょう。それが、無駄な逆張りを防ぐポイントになります。
ボリンジャーバンドと他の根拠を併用する
高値掴みや安値掴みを防ぐためには、「ボリンジャーバンドを単体で使わない」ことが大切です。バンドの±2σや±3σは確かに極端な価格帯を示していますが、それだけで反転を判断するのは危険です。特にトレンド中は、バンドに沿ってそのまま価格が進行することも多く、逆張りではなく順張りでの対応が必要な場面もあります。
そこで重要になるのが、“複数の根拠”を持った判断です。たとえば、ボリバンの端に到達しているだけでなく、同時に水平線やトレンドライン、ローソク足のパターン(例:ピンバーや包み足)といった反転のサインが出ているかをチェックしましょう。
私自身も、昔は「ボリバンが広がったから反転するだろう」と安易に逆張りして失敗していました。でも、そこに水平線やチャートパターンを組み合わせるようにしてから、無理なエントリーが激減し、勝率も上がりました。

ボリンジャーバンドを主軸に使うのであれば、他のテクニカル要素と組み合わせて“反転しやすい場所”かどうかを多角的に見極める意識を持ちましょう。
チキン利食いを防ぐにはどうすればいいか
チャートの先をイメージする力が重要
チキン利食いとは、少しの含み益ですぐに利確してしまい、結果として本来取れたはずの利益を逃してしまう行動です。その原因の多くは、チャートの“先の展開”をイメージできていないことにあります。「これ以上持っていたら反転するかも」という不安から、ほんの数ピップスで利確してしまうのです。
相場は常に上下に揺れ動くため、多少の戻しは織り込み済みで動いていることが多く、持つべき場面で耐えられないと利益を伸ばすのは難しくなります。だからこそ、エントリーする時点で「どこまで伸びる可能性があるか」を想定し、その到達イメージを明確にしておくことが大切です。
私も以前は「せっかく含み益が出たんだから、減る前に利確しよう」と考えていましたが、それでは毎回3〜5pipsで終わってしまい、大きな利益にはつながりませんでした。

目標までのシナリオを描きながらエントリーすることで、途中の値動きにも動じず、冷静に利確判断ができるようになります。まずは「利確ポイントの事前決定」から始めてみましょう。
平均足で利確タイミングを視覚化する
チキン利食いの対策として、平均足を使う方法は非常に有効です。平均足は、一定期間の価格の平均値を視覚的に表現するため、通常のローソク足よりもノイズが少なく、トレンドの継続や転換を捉えやすくなります。この特性を活かして、「平均足の色が変わるまで保有する」というルールを取り入れると、利確のタイミングに迷わなくなります。
たとえば、ロングエントリーした後に平均足が青のままであれば、そのトレンドは継続していると判断し、色が赤に変わったときに利確を検討する。というような使い方です。こうすることで、根拠のある保持が可能になり、不安から早々に利確してしまうことが減ります。
私自身も以前は「なんとなく上がったからもういいや」とすぐ決済してしまっていましたが、平均足を取り入れてからは「色が変わるまでは保とう」と明確な基準を持てるようになり、結果として利益を伸ばせるようになりました。

平均足は1分足や5分足など短期足で使いやすく、普段のトレードにもすぐに取り入れられます。チキン利食いに悩んでいる方は、まずはこの視覚的なサポートを活用してみてください。
分割決済で“持つ練習”を積み重ねる
チキン利食いを防ぐために効果的なのが、「分割決済」のテクニックです。ポジションを複数のロットに分けて段階的に利確することで、心理的な安心感と利益の最大化の両方を狙うことができます。
以下のようにシンプルな分割決済から始めるのがおすすめです。
- 2万通貨でエントリー
- 1万通貨を+5pipsで先に利確(利益の確保)
- 残り1万通貨を+15pipsを目安に保有(利益の伸ばし)
このように「一部利確+一部保有」を実践することで、「全部すぐに決済してしまう」というチキン利食いを減らす練習になります。
私も以前は、含み益が出た瞬間にすべてを決済してしまっていましたが、分割決済を導入してからは精神的に余裕が持てるようになり、結果としてトレンドに乗ることも増えてきました。

“全部持つ”のではなく、“一部だけでも伸ばす”という感覚から始めるのが、実践的なステップです。
ライブでは勝てるのに一人だと勝てない理由
環境認識と根拠ある判断を自分で再現できていない
ライブ配信中は勝てるのに、一人でトレードをすると結果が出ないという方は、環境認識やエントリーの根拠を“自分の言葉で再現できていない”ことが原因の一つです。ライブでは私が「ここは押し目買いのポイントです」「今は高値掴みに注意です」といったナビゲートを行っており、その流れに乗ることで自然と良いトレードができている状態です。
しかし、一人になるとそのナビがなくなり、自分で環境を認識し、判断する必要が出てきます。ここで「なぜエントリーするのか」「どの時間足を見ているのか」「どんな根拠があるのか」が言語化できていないと、なんとなくの感覚でポジションを取ってしまい、失敗につながります。
私自身、かつては「ライブなら勝てるのに…」と感じていた時期がありました。そのときは、エントリーポイントだけを真似て、環境認識を軽視していたのです。

ライブで学んだことを活かすには、「なぜそのエントリーが有効だったのか」を自分なりに整理し、再現できるようになることが重要です。
市場・時間帯・トレンドを意識した判断力を持つ
トレードの結果は、相場の時間帯や市場の特性によって大きく左右されます。たとえば、東京時間は比較的穏やかで、欧州・NY時間はボラティリティが高いなど、それぞれに傾向があります。ライブ配信では、その時間帯や市場に合わせた戦い方をしているため、トレードがスムーズに進むのです。
一方で、一人でトレードをしていると、その時間がどの市場に当たるか、どんな特徴があるのかを意識できていないことが多く、うまく噛み合わないトレードになりがちです。また、時間帯によって有効な戦術も変わるため、すべての時間で同じアプローチをしても通用しません。
私も以前、朝でも夜でも同じ戦い方をしていて、なぜか勝てるときと勝てないときがあると悩んでいました。しかし、「今はどの市場が動いているのか」「どのトレンドが優勢か」を考えるようになってから、エントリーの精度がぐっと上がりました。

一人のときこそ、市場の時間帯、通貨の特性、トレンドの有無などを意識した“時間軸の戦略”を持つことが大切です。
試行錯誤と検証を通じて“勝ちパターン”を見つける
一人で勝てないもう一つの理由は、「自分なりの勝ちパターンがまだ見つかっていない」ことです。ライブ配信では私の経験をベースに、勝ちやすいタイミングや手法を紹介していますが、それを自分のトレードに落とし込むには、検証と試行錯誤が欠かせません。
どんなに良い手法を学んでも、それを自分のものにするには“自分で繰り返し試してみる”必要があります。最初は思うようにいかなくても、勝てたパターンと負けたパターンを記録し、何がよかったのか、何が悪かったのかを分析していく中で、自分のスタイルが固まっていきます。
私も最初から今のようなトレードができていたわけではありません。何度も失敗を重ね、その中で「この形のときは勝ちやすい」「この時間帯は狙わない方がいい」といったルールを構築していきました。

焦らず、ロットも最小単位で構わないので、自分の検証を繰り返すことが、最終的には“ひとりでも勝てる”力を身につける近道です。
ゴールデンクロス・デッドクロスで勝てない原因と対策
クロスは“サイン”であってエントリーポイントではない
ゴールデンクロスやデッドクロスと聞くと、それだけでエントリーの合図だと思ってしまいがちです。実際、多くの書籍や解説でも「クロス=買い/売り」と紹介されていますが、相場の実戦では必ずしもその通りに機能するとは限りません。むしろ、クロス直後に逆行するケースも多く、初心者が最初につまずくポイントの一つです。
クロスは、あくまで“トレンド転換の可能性を示すサイン”です。その時点でエントリーするのではなく、「これからどう動くか」を探るための材料として活用すべきなのです。特に、移動平均線は“遅行指標”であるため、クロスが起きた時点ではすでに価格が大きく動いた後ということも少なくありません。
私も初心者の頃、クロスが出た瞬間に飛び乗っては損切りを繰り返していました。そのたびに「なんで逆行するんだ」と悩んでいましたが、今思えば“サイン”と“タイミング”の違いを理解していなかったからです。

クロスはその後の戦略を組み立てるための“きっかけ”と捉え、エントリー自体は別の根拠で判断するようにしましょう。
クロス後の押し目買い・戻り売りが有効な戦略
ゴールデンクロスやデッドクロスを実戦的に活用するには、クロス直後に飛び乗るのではなく、その後の押し目や戻りを待ってからエントリーするのが効果的です。
これはグランビルの法則にも通じる考え方で、クロスはあくまで「方向性の確認」であり、実際の仕掛けは調整が入ったポイントで行うのが理想です。
クロスが発生するということは、すでに短期の移動平均線が長期線に近づいてきており、ある程度トレンドが進んだ状態です。そこから一度押し目や戻りが入って再度トレンド方向に進んだタイミングが、最も信頼性の高いエントリーポイントになります。
私自身、クロスで何度も失敗した経験から、「クロス→押し目待ち」に戦略を切り替えたことでトレードの精度が上がりました。特に5分足や15分足でクロスが出た後、短期の調整を見てタイミングを測ることで、無駄な逆行を防げるようになったのです。

エントリー前に「もう一段階待てるか」を意識するだけでも、トレードの成功率は大きく変わってきます。
上位足とグランビルの法則を合わせて使う
移動平均線のクロスを使う際にさらに効果的なのが、「上位足との組み合わせ」です。たとえば、5分足でゴールデンクロスが出ていても、15分足や1時間足が下降トレンドであれば、その上昇は一時的な調整で終わる可能性があります。逆に、上位足が同じ方向に動いていれば、クロスの信頼性も格段に高まります。
ここで活用したいのがグランビルの法則です。移動平均線の位置関係や、価格の押し目・戻りがどこで起きているかを見ることで、エントリーポイントをより客観的に判断できるようになります。
「移動平均線に対して価格が離れすぎていないか」「反発がどの角度で起きているか」などを意識することで、クロスを“根拠ある戦略”へと変えることが可能になります。
私も以前はクロス単体で判断していましたが、上位足のトレンドと合わせて見るようにしてから、「これは本当にトレンドが発生しているのか?」を冷静に判断できるようになりました。

クロスを活かすには、時間軸ごとの役割を理解し、グランビルの法則を参考にすることで、より精度の高いトレードが実現できます。
時間足で売買判断が逆になる時の考え方
わからないときは“やらない”選択が最善
異なる時間足で売買サインが逆になっている場面に出くわすと、「どっちに従えばいいんだろう」と迷ってしまうことがあります。たとえば、5分足では買いシグナルが出ているのに、15分足では売りの流れが続いているようなケースです。こうした時に無理にエントリーしてしまうと、結局方向が定まらないまま損切りになる可能性が高まります。
相場には“やるべき時”と“やらないべき時”があります。トレードの勝率を上げるためには、わからない・迷っている時には思い切って「今日は見送る」という判断をする勇気が必要です。これは、初心者だけでなく中・上級者にも共通する大事なスタンスです。
私自身、以前は「せっかくチャートを開いたんだから」と無理にポジションを取っていましたが、結果的には“無駄なエントリー”が負けの原因になっていました。

方向感に確信が持てない時は、むしろ“やらない”という判断こそが最も正しいトレード戦略になります。
複数時間足の到達点と反発余地を見極める
時間足によって売買判断が分かれるときは、「各時間足が今どの位置にいるか」をしっかり確認することが重要です。
たとえば、15分足ではすでにボリンジャーバンドの+3σに到達していて過熱感がある一方、5分足ではまだ上昇の勢いが残っているような場面では、“反発が起こる可能性”と“その余地”を多角的に見極める必要があります。
単に「5分足が買い」「15分足が売り」と表面的に判断するのではなく、それぞれの時間軸での到達点やトレンドの強さ、勢いの残り具合を見ていくことが大切です。どの時間足が優先されやすいか、またはすでに目標を達成しているのかを判断材料に加えることで、無駄な逆行を減らすことができます。
私も以前は「時間足がバラバラだから難しい」と避けていましたが、今では「15分足はすでに伸び切ったから、5分足の動きは短命かも」など、背景を想定して判断するようになりました。

時間軸の違いは“視点の違い”です。どの足が“伸びしろ”を持っているかを見極めることが、判断力を高めるコツです。
迷ったら上位足の方向性を優先する
複数時間足で売買の方向性が異なる場合、基本的には「上位足の方向に従う」ことが安定したトレードにつながります。上位足ほど全体のトレンドを表しており、短期足の逆行はあくまで一時的な調整に過ぎないことが多いからです。
たとえば、1時間足や4時間足で下降トレンドが続いている中、5分足で短期的な上昇があっても、それは「戻り売りのチャンス」と見る方が自然です。短期足の逆張りを狙うよりも、上位足の流れに沿った方向で押し目や戻りのポイントを探した方が、勝率も安定します。
私も過去に「1分足で上がってるからロング」と判断し、上位足の下落トレンドに逆らってエントリーして損失を出した経験が何度もあります。今では、「短期足はあくまでエントリーのタイミングを見るもので、方向は上位足に従う」と意識しています。

迷ったときは、チャートをズームアウトして上位足の流れを再確認し、自分が本当に“優位性のある方向”にポジションを持っているかをチェックしましょう。
エントリー後に逆行してしまう理由と対策
“追っかけトレード”は逆行を招きやすい
エントリーしてすぐに逆行してしまう多くのケースは、値動きを“追っかけるように”エントリーしていることが原因です。チャートが急騰したからロング、急落したからショートと、反射的に飛び乗るトレードは、トレンドの終点を掴んでしまうリスクが高く、逆行に巻き込まれる可能性が大きくなります。
相場は、動いた直後に一旦戻す“反動”が出やすいため、飛び乗るほど逆に持っていかれる展開になりやすいのです。特に初心者の方は、「乗り遅れたくない」という焦りからこのようなエントリーをしてしまう傾向があります。
私もトレード初期は、「今だ!」と思って飛び乗ってはそのまま逆行される、という苦い経験を繰り返していました。今はむしろ「勢いが出たときこそ冷静に一呼吸置く」ことを意識しています。

エントリーは、感情ではなく“根拠ある準備”のもとに行うものです。チャートの動きに反応するのではなく、あらかじめ決めたパターンが揃った時だけエントリーするという姿勢が大切です。
ブレイクの伸びしろとタイミングを見極める
ブレイクアウトは大きく取れるチャンスでもありますが、飛び乗るようにエントリーしてしまうと、その直後に反転されて損切り…というケースも少なくありません。これは、ブレイクの“伸びしろ”や“相場の背景”を確認していないことが原因です。
ブレイク前に以下の項目を確認しておくことが大切です。
- 上位足が同じ方向に向かっているか
- 直近に強い抵抗帯・サポート帯がないか
- 市場の流動性が高く、ボラティリティが出やすい時間帯か
- 経済指標の前後などで、急変リスクがないか
私も、ブレイクした瞬間に反射的にエントリーしては、すぐに反転される経験を何度もしてきました。しかし、今は伸びしろの有無や時間帯を含めた環境認識を重視することで、ダマシに引っかかることが減ってきました。

単なる“抜けたからエントリー”ではなく、「抜けたあとに伸びる余地があるか?」という視点を持つことで、無駄な損失を防ぐことができます。
時間帯と市場の特徴に合わせてトレードする
エントリー直後に逆行する原因の一つに、時間帯の特徴を意識していないことがあります。相場は時間帯ごとに動き方が大きく異なり、それぞれの市場には特有のクセがあります。
特に、以下のような特徴を押さえることが大切です。
- 東京時間(9:00〜15:00):値動きが穏やかでレンジになりやすい
- ロンドン時間(16:00〜24:00):欧州勢の参入でトレンドが出やすい
- ニューヨーク時間(22:00〜翌6:00):米指標や株価の影響で急変動が起きやすい
これらの時間帯特性を無視して、「どの時間帯でも同じように動く」と思ってエントリーしてしまうと、逆行される可能性が高まります。さらに、市場オープン直後や経済指標発表時はボラティリティが急変しやすいため、エントリーの精度が問われます。
私自身、かつては時間帯を気にせずどの時間も同じスタイルでトレードしていましたが、現在はロンドン時間やニューヨーク時間に絞って戦略を切り替えるようにしています。その結果、逆行のリスクを減らせるようになりました。

トレードの質を高めるには、「いつやるか」という時間軸の意識も欠かせません。
直近の高値・安値を基準に保有判断をする
エントリー後に逆行してしまうと、すぐに損切りしたくなる気持ちはわかります。しかし、その逆行が“本当に損切りすべきレベルまで来ているのか”を判断するには、チャート上の基準が必要です。そこで意識したいのが、直近の高値や安値です。
たとえばロングでエントリーした場合、価格が下がっても直近の安値を割らなければ、まだ“上昇継続の可能性”は残っています。逆にショートなら、直近の高値を超えない限りは保持を検討できます。基準がないと、少し逆行しただけで不安になり、早期に手仕舞いしてしまうことになります。
私も以前は、ほんの数pips戻っただけで焦って損切りしていましたが、「安値を割るまでは持とう」と決めてからは、途中の揺れに一喜一憂しなくなりました。

ポジション保有中は、チャートの“明確な基準”に従って冷静に判断することが、結果的に利益を伸ばす鍵になります。
よくあるトレードの落とし穴とその対処法
今回は、FX初心者が特に悩みやすい「エントリー後の逆行」「高値掴み・安値掴み」「チキン利食い」「クロスでの失敗」など、よくあるトレードの落とし穴とその対処法について、実体験も交えながら詳しく解説しました。
すべてに共通するのは、“感覚ではなく根拠で判断する”ことの重要性です。ボリンジャーバンドや移動平均線、平均足といったテクニカル指標を正しく使うだけでなく、マルチタイムフレーム分析や時間帯の特性を意識することで、無駄な逆行や損失を避けやすくなります。
また、ライブ配信では勝てるのに一人だと勝てないという悩みも、「環境認識」「根拠あるエントリー」「検証と反省」を積み重ねることで、徐々に自分の力で再現できるようになるでしょう。
どれか一つだけを改善するのではなく、自分のトレードを客観的に見直し、少しずつ精度を上げていくことが、長期的に勝ち続けるためのポイントです。

まずは一つ、自分が最も当てはまる課題に取り組んでみてください。小さな改善が、安定したトレードへの第一歩になります。
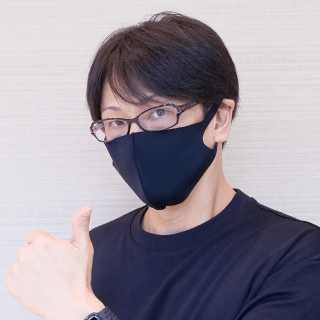
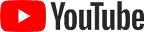 チャンネル登録者数8.1万人
チャンネル登録者数8.1万人